レポート
2025年4月3日(木)
2025イベントレポート「国立工芸館☆春待ちスペシャル「たんけん!こども工芸館~リピート・リピート・モビールづくり」」
 終了18歳未満 入場無料
終了18歳未満 入場無料 
国立工芸館☆春待ちスペシャル「たんけん!こども工芸館~リピート・リピート・モビールづくり」
国立工芸館
開催日 2025年2月23日(日・祝)
- 彫刻・立体
- プロダクト
- ワークショップ
- 工芸
- デザイン
- 伝統
- 人間国宝
- オブジェ
目次
工芸とデザインを専門に扱う国立工芸館では、2025年2月から3月にかけて「国立工芸館☆春待ちスペシャル たんけん!こども工芸館」と題した3つのイベントが開催されます。その第一弾として2月23日(日・祝)に行われたのが「リピート・リピート・モビールづくり」です。
タイトルにある「リピート」は、同時期に開催された展覧会「反復と偶然展」にちなんだもの。模様や形が連続することで生まれる表現のおもしろさを、工作を通して体験する試みです。会場では小学生を中心とした子どもとその家族約30名がイベントに参加し、思い思いのモビールづくりに熱中していました。

冬ならではの光を楽しむ
国立工芸館のある石川県金沢市では、冬になると雪国特有の光景が街のあちこちで見られます。イベント当日も前の週から降り続いた雪が美術館の前庭を白く覆い、にわかに日が差す時間帯はまぶしく感じるほど。

再び小雪が舞い始めたお昼過ぎ、イベントの参加者たちが、続々と会場に集まってきました。
今回制作するのは、3色の金属シートを使ったモビールです。金属シートはとても柔らかい素材で、子どもでもハサミで切ったり、手で簡単に折り曲げたりすることができます。さらにボールペンを使って表面に模様を加えれば、その凹凸が光を反射して、さまざまな表情が生まれます。
できたパーツをテグスで繋いで吊るせば、光が揺らぐモビールのできあがり。窓辺に飾って光を集める“サンキャッチャー”にヒントを得て、冬の室内を明るくするアイテムとして企画されました。


リピート・リピート
会場を訪れた参加者たちは室内に展示された制作見本を見つけ、「こんなのができるんだって」「どうやってつくるのかな?」と話したり、机の上の素材や道具と見比べたり。
「やってみたい」という創作意欲が高まるなか、まず始まったのは「形と模様のエクササイズ」。会場のスクリーンには大きな丸が1つ映し出されました。イベントの進行を務める特定研究員の日南日和さんが「この丸い形を、2つ並べるとどうなるかな…?」と呼びかけると、子どもたちは口々に「雪だるま!」「めがね!」と反応します。

丸が3つなら花見団子、6つを逆三角形に並べればぶどう、画面いっぱいに敷き詰めれば水玉模様というふうに、単純な形でも繰り返し“リピート”することで、さまざまなものに見立てて楽しむことができます。
複雑で緻密な工芸作品も、実はこうして同じ形の繰り返しによってつくられたものが少なくありません。
イベントと同時期に開催された「反復と偶然展」は、模様を連続させたり、規則的な動作を反復したりすることによって生まれるリズムや思いがけない表情に光を当てた展覧会です。
たとえば昭和期に活躍した竹工家・林尚月斎の《花編放射文盛器》は、花や蝶を思わせる模様が特徴的な作品ですが、これも規則的に竹を編むという動作の繰り返し、放射状の線と楕円形の連続によってつくり出されたものです。


素材の感触と偶然の発見
エクササイズを通してリピートのおもしろさに触れた会場の参加者たちも、いよいよ作品づくりに取り組みます。最初は練習も兼ねて、金属シートを好きな形に切ってみるところから。
シートの端っこから遠慮がちに小さな丸を切り出す子もいれば、全長を活かして大胆なカットを入れる子も。

このイベントでは、大人も“付き添い役”ではなく1人の参加者として材料が用意されています。迷いなく手を動かす子のそばで「好きな形って言われると、案外難しい」という声も聞こえる一方、全てのシートをあらかじめ4等分してからハサミを入れる計画的な大人もいて、この時点ですでに、いろんなモビールが生まれる予感。
ハサミを入れる感触が気に入ったのか、七夕飾りのような切り込みを入れる作業に熱中する子もいました。金属シートはハサミを入れるときに独特の抵抗感があり、張りや反りなど、紙とは異なる感触を楽しめる素材です。


蛇の形にしようと渦巻き状にハサミを入れていた親子のテーブルでは、バネのような、螺旋状のパーツができていました。
今回のイベントを企画した日南さんは、こうした素材から得られる偶然のおもしろさにも着目しています。「以前、同じ金属シートを使ってバッジづくりをしたとき、練習用に使った端切れを『きれいだから』と気に入って持ち帰っている子がいて。モビールなら、そういう発見も作品の一部として活かすことができますし、手でクシャッと丸めたり、シワになったりした部分の表情も、楽しみながら取り組んでもらえると思います」

各々好きな形を切り出したら、今度はそのパーツに模様を加えます。ボールペンで線を描き、インクを拭き取れば表面に凹凸だけが残ります。
「たくさん書きこむと、もっともっとキラキラになるよ」というヒントから、参加者たちは、小さなパーツ一つひとつを埋め尽くすように模様を描き込んでいきます。葉脈のような線の模様、細かい粒の水玉模様、ひらがなやアルファベットのような文字も、繰り返し、連続させていくことで新しい模様になります。


また、繋げるパーツの形にテーマを持って“リピート”させている人もいました。家族で協力して、ハートや動物、蝶々、恐竜など、同じ形をたくさんつくれば、ひとつの大きな作品に仕上げることもできます。
色違いのシートを折り紙の要領で合体させたり、シート同士を垂直に交差させて組み合わせたり。大人も子どもも自由な発想で、自分の技法を見つけていました。
ある男の子は、勢い余ってシートに大きな穴を開け、がっかりした様子。すると、隣で制作していたお母さんが「それも模様にしようよ」と提案するなど、時間が進むにつれて大人の発想も柔軟になっていくのを感じました。

「次はなにつくろっかな〜」
参加者のテーブルを回っていると、鼻歌まじりで「次はなにつくろっかな〜」という子どものつぶやきも聞こえました。
このモビールづくりでは、同じ工程を何度か繰り返しながらパーツを増やす、手順のリピートが必要になります。1つのパーツをつくるときに得た発見や気づきをもとに、また次のパーツをつくる。その連続性のなかでコツをつかんだり、先につくったパーツがヒントになって新しいアイデアが浮かんだりすることもあるようです。

こうして自分の手で作品をつくる体験は、鑑賞者として美術作品に向き合うときにも、新しい視点を与えてくれます。つくるプロセスを知ることで、技法に対する理解が深まるだけでなく、制作を通して得られる達成感や探究心は、どうしてこんな作品をつくろうとしたのかという、作者の動機を想像する手がかりにもなります。
美術館で開催されるワークショップの良さは、参加者がそのあと展示室に立ち寄れること。今回のイベントに参加した子どもたちには、展覧会を見ながら作品の記録ができるワークブック「たんけんかのおぼえがき」がお土産としてプレゼントされました。
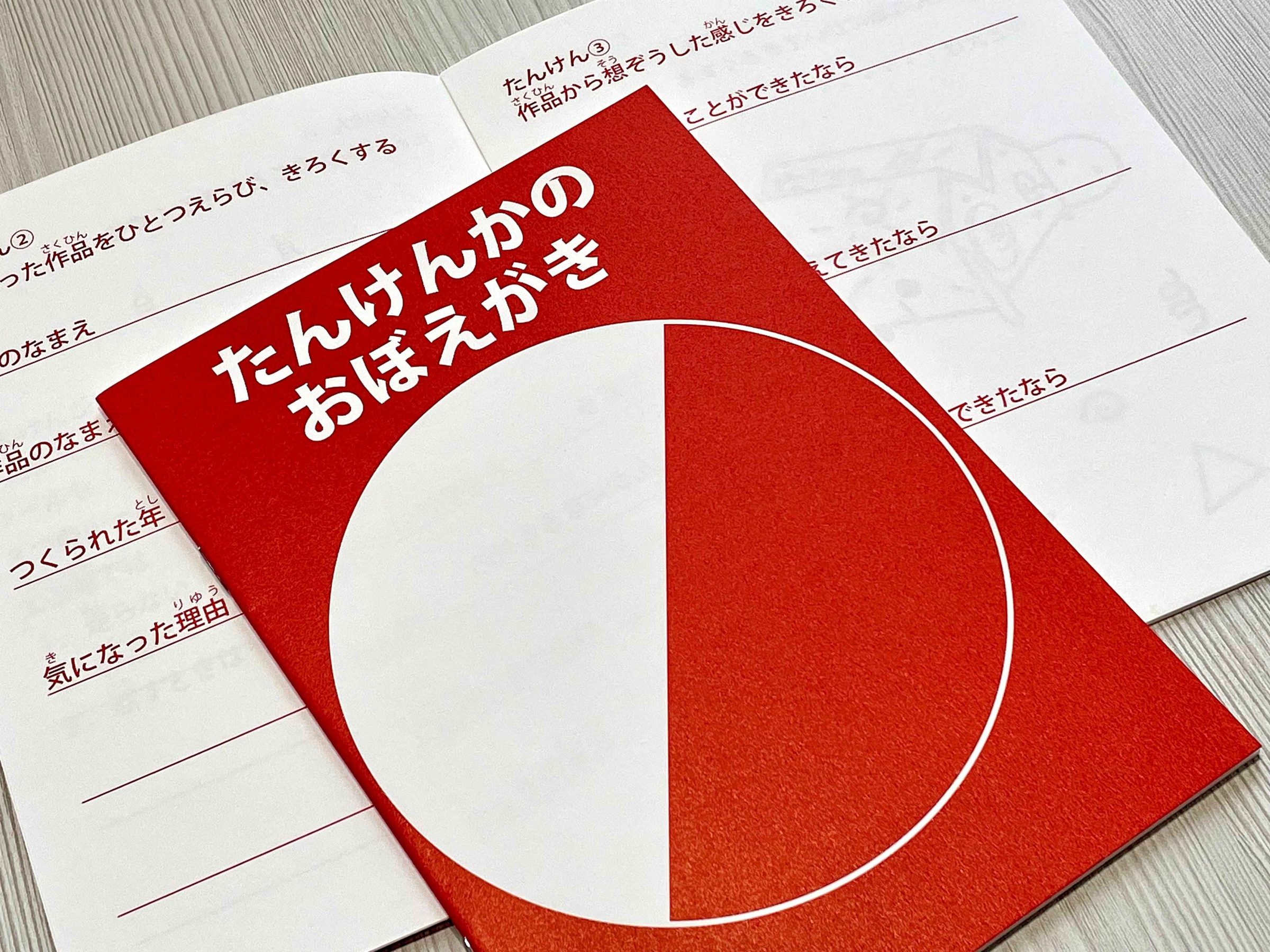
このワークブックは、美術館を訪れた子どもたちが、探検家気分で展示室をめぐるためのツール。お気に入りの作品についてスケッチしたり、作品名などの情報を記録したり、ページをめくるごとにいろんなワークができるようになっています。
会場でワークブックを手にした子どもたちの多くは「絶対見たい」「はやくはやく!」と言いながら、イベント後に展示室を訪れていたようです。5歳の男の子と一緒に参加したお父さんが「子どもがまだ字を書けないので、代わりに片っ端から作品名を書かされました(笑)」と話す横で、本人はとても満足そうな様子でした。
さて、イベントも終盤になると、続々と完成した作品が窓辺に並びます。

いち早く完成させた子どもたちは、柱や壁など、別の場所に移動して見え方を比べたり、息を吹きかけて揺らしたり。いろんな角度から眺めて楽しんでいました。
一方、「では、そろそろ片付けを」という終わりの合図に、「え〜!」と慌てた声を出したのは、大人たちのほうでした。
テーブルの上には、まだこれから模様を描き込むべく用意されたパーツがたくさん並んでいる人もちらほら。時間が迫るなか、なんとか良い作品に仕上げようとする参加者の表情は、仕事さながらの真剣さ。そんなお母さんに代わって、アンケート用紙の記入を引き受けている子どもたちもいました。
家族で一緒につくるという体験は、親が子どもの成長を実感するだけでなく、子どももまた、いつもの保護者の顔とは少し違う、遊び仲間のような一面を発見する機会にもなります。


幸いこのモビールはボールペンとハサミ、カッターマットの代わりになるものさえあれば、家に帰ってから続きを制作することができます。担当の日南さんによれば、参加者から後日「おうちでも続きをつくっている」という報告もあったそう。
完成した作品や、つくりかけのパーツと一緒に、「次はなにをつくろう」「何を見よう」というワクワクする気持ちを持ち帰ることが、イベントの何よりの成果なのかもしれません。
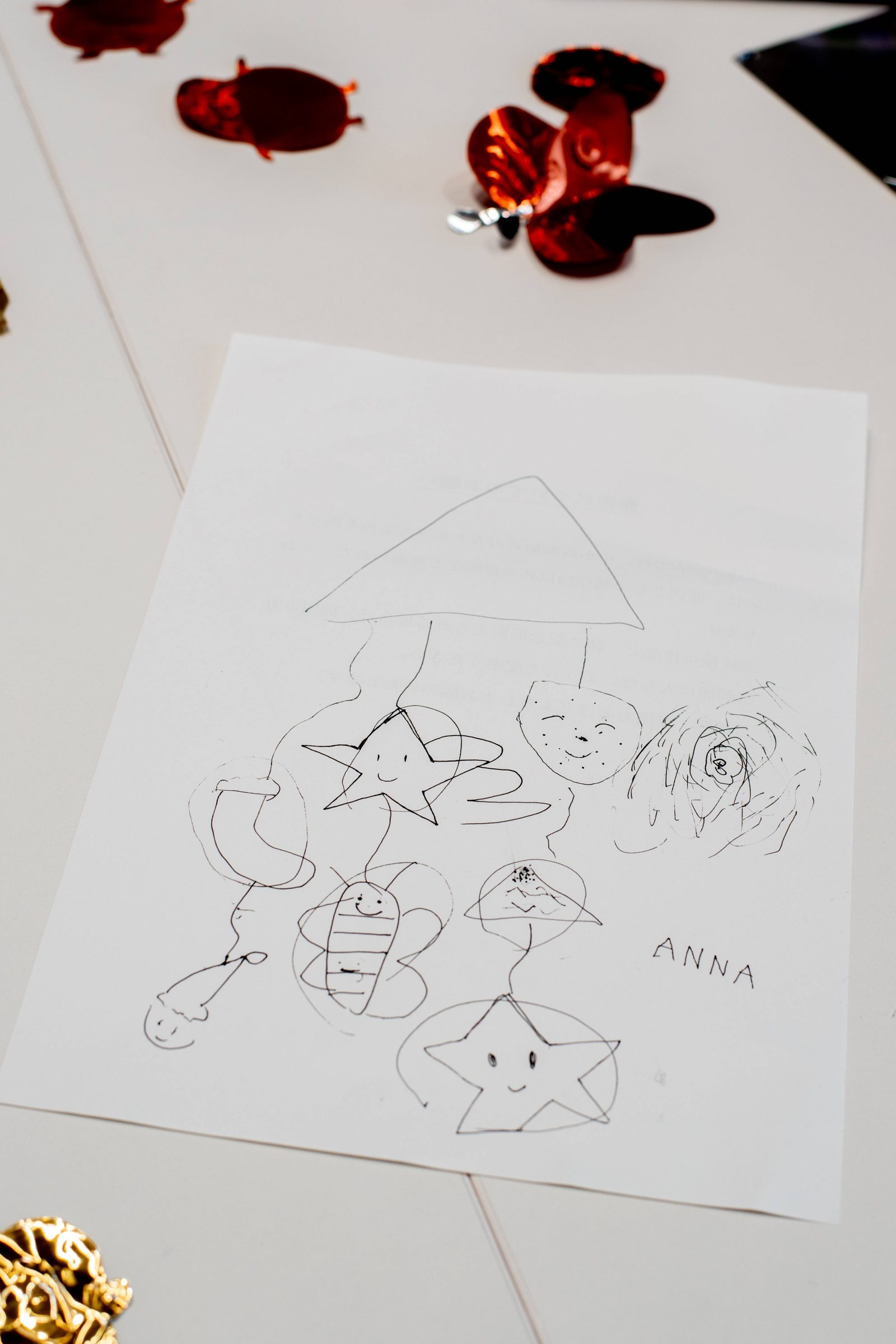
取材日: 2025年2月23日
編集: 高橋佑香子
Photo: haruharehinata
※の写真を除く